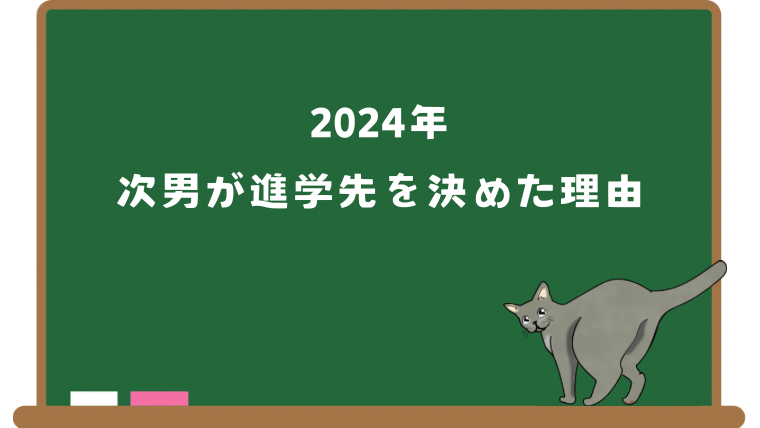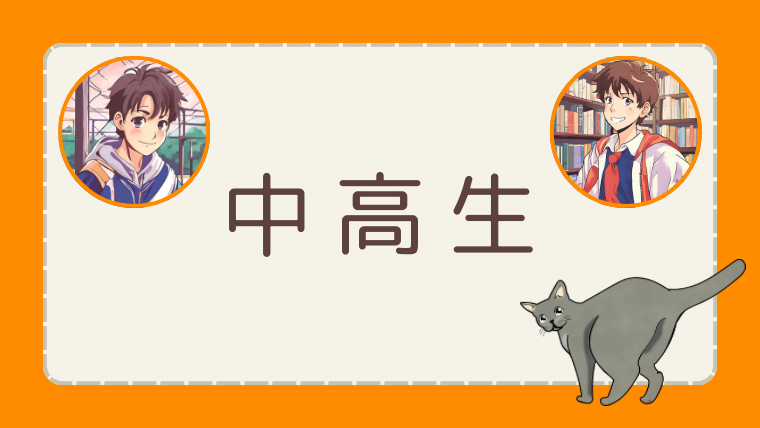【勉強と部活の両立の仕方】塾なし。週6部活でも、国立大現役合格した勉強法。
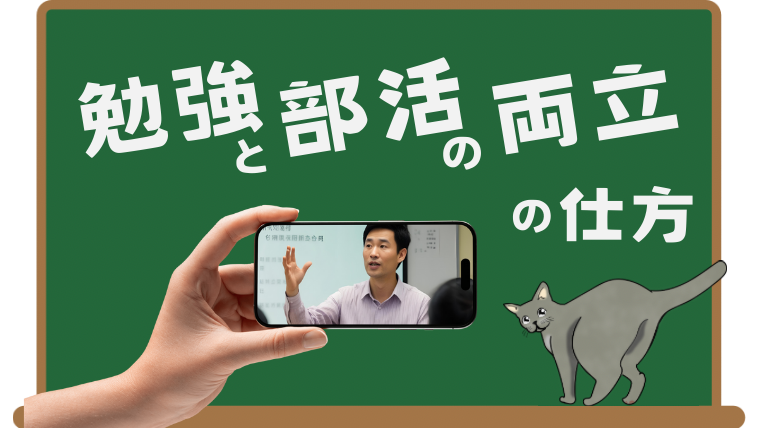
「高校に入ったら、勉強も部活もがんばりたい!」と希望に胸膨らませる春。
ところが数カ月経つと疲れがたまり「今まで授業中寝たことなんてなかったのにどうしても寝ちゃう」なんてこともあるかもしれません。
・通学時間が長くなったことで、今までよりも早く家を出て帰る時間も遅くなり
・受験勉強でなまっていた体に一気に襲い掛かる高校部活の運動量
・中学までとは違う授業スピードと難易度アップ
目まぐるしく変わる日々に睡眠不足と疲労が蓄積される頃ですね。
わが家の息子たちも「勉強したくてもなかなか時間がとれない中」なんとか工夫して勉強と部活の両立を頑張っていました。そして長男は2019年。次男は2024年に2人とも公立高校から塾にも通わず国立大に現役合格できました。
この記事では2人が行っていた勉強方法を紹介します。
「参考書」「問題集」「過去問」のみ。2000年生まれ夜型長男の勉強法。
すきま時間の活用

わが家は兄弟ともにバスケをやっていました。平日は毎日朝練で、家を出るのは6時半。帰宅は20時頃になるのが普通。土日も練習や大会、遠征。休みは週一回ありましたが(それでも朝練はある笑)「もはやトレーニングだけの日は休みみたいなもの」と言っているような状態でした。
※朝練に関しては月曜日と金曜日は自由参加だったのですが、みんなやりたいから休む子はほとんどいませんでした。
そうなってくるとアレもコレもはできません。
一日24時間なのは皆同じ。優先度を決めてできないことは切り捨てていくしかありません。
- 授業はしっかり聞く
- 宿題はやる
- 部活優先。バスケノートも書く。
- テスト勉強は部活が休みになったときに集中してやる
こんな感じです。
ただ重要なのは以下3点。
- 授業についていけなくなったら終わり
- 取り戻すことなんてできない
- わからないところは先生や友だちに聞いて疑問を残さない
絶対にわからないところをそのままにすることはしませんでした。
授業についていけなくなったら終わりです。もう取り戻せません。
そしてすきま時間をどう使うかが工夫のしどころ。
うまく「できることをできるとき」にやっていました。
うちは通学時間がバスを乗り継いで1時間くらいでした。
- バス停でバスを待つ間に古文や英単語を覚えたり
- 宿題はなるべく学校ですませる工夫もしていました
先生によっては授業中でも「早く問題の解けた人は宿題やってもいいよ」と言ってくれる人もいたようです。「どれだけ学校で宿題を終わらせられるかが大事」なんて言ったりしていました。あと「人に教える」のもかなり自分の理解が深くなりいいことのようでした。
他には、お昼休みは体育館でバスケしたいから
- お弁当は3時間目と4時間目の間に食べて、昼休みはバスケする
なんていう工夫もしていました。
家に帰り着く頃には相当疲労もたまっているので、本当はご飯食べてお風呂入って寝るだけにしたいところ。日中できることがあったら、なるべく日中にこなしておくのがいいようですね。

勉強の時間を取れないことの焦りを子どもの方が感じてしまうこともあります。
そんなときは問題を整理してあげましょう。
今やるべきこと=優先度 の確認です。
- 次の大会で勝つための練習→今しかできないこと
- 定期テストや受験の勉強→後でできること
こんな感じで整理できたら、自信を持って今やるべきことに集中していいと伝えてあげてください。アレもコレもはできません。部活に集中していた子の切り替えた時の爆発力は素晴らしいものです。
ただ授業についていけなくなったら本当に終わりなので、日々の小テストなどには気を配ってあげてください。
「次おんなじ問題出たら100点とれるの?」
「受験のときにできるかどうかが大事なんだよ」
と繰り返し伝えることで目的がはっきりします。
目的は小テストで100点をとることではなくて、希望の大学に合格することです。
全体像の把握からの受験勉強開始
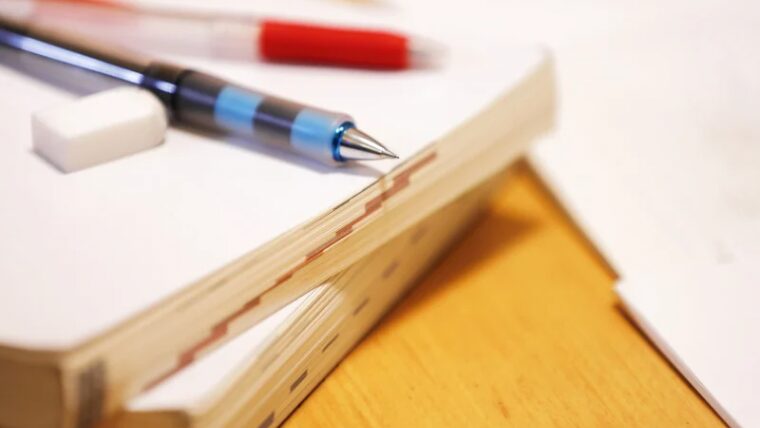
長男はなかなか計画的で、1年生の頃から受験に向けて振り返りをしていたそうです。
本格的に受験勉強を始めたのは3年生の部活引退後の6月。とは言っても7月に学校祭があったので、それが終わってからですね。部活から勉強に切り替えるタイミングで青春の集大成みたいなイベントがあって本当にちょうどよかったです。
長男は「まず過去問にざっと目を通して全体像を確認してから始めた」そうです。
現在地と目的地の確認ですね。
2000年生まれの長男にとっては「参考書」「問題集」「過去問」これだけが頼れる受験アイテムでした。今ほどスマホや動画学習が普及してはいませんでした。
受験科目の数Ⅲに苦戦していたので、塾に通うことも検討し見学に行ったこともあったのですが結局は合わずに独学で頑張ることに決めました。田舎には数Ⅲを教えられる先生は少なかったのです。
数学は「青チャー」を利用していました。
あともしまだ「ドラゴン桜」を観たことがなかったら、観た方がいいですよ。
うちは兄弟2人とも観ていました。勉強方法もためになるし、何より社会の見え方が変わると思います。
場所を変える

これは兄弟揃ってですが自宅ではどうも勉強に集中することができないようでした。
外で勉強してやる気になるならどんどん外でやるといい。
人目もあってダラダラできないし、周りには勉強している仲間たちもいてモチベアップに繋がります。
- 学校の図書室
- 公共の図書館
- コミュニティセンター
- 商業施設
- ミスド、ケンタッキー、コメダなど
あんまり受験直前だとインフルとかうつされても困るから行けないけど、それまでは使える物使える場所なんでも使いましょう。他校の受験生とも場所の取り合いになりますががんばって!
自分のスタイルで勉強。模試の結果が悪くても折れない。
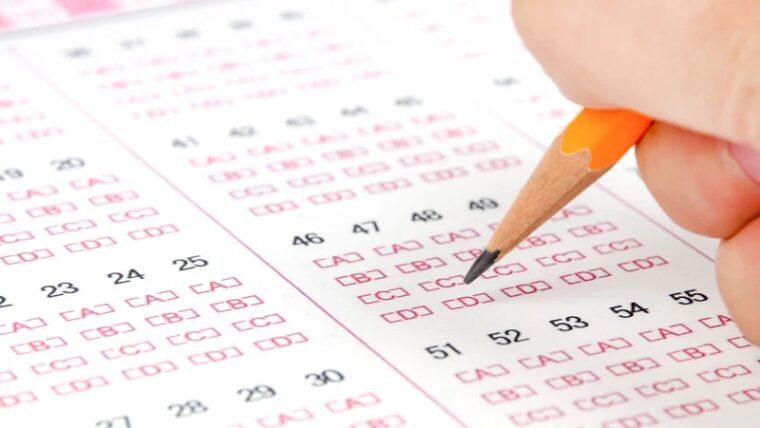
長男は完全に夜型で、家族が寝静まるまで仮眠をし、みんなが寝た頃に起きて勉強をしていました。その子によってやる気の出るタイミングは違うと思うので、自分なりのスタイルが見つけられたらいいですね。
それでもちょっと休憩のつもりが、メガネもかけたまま部屋の灯りもつけたまま開いた本を両手に持ったままベッドで横になって朝を迎える、なんてこともありました。それでもいい。がんばってる証拠です。
目指すのは全国から受験生が集まる大学。市内では進学校でも、ライバルたちは全国にいます。2年生までに教科書を終わらせ3年生の1年間は受験に特化した授業を受けている私立の子たちもいます。もちろん浪人生も。
模試の成績は一向に伸びませんでした。伸びないどころか下降して、そのうち親に見せなくなりました。あとで見たところ、秋の模試で確かE判定だったと思います。
ですが学校の先生もよく言いますが部活生の伸びはここからです。夏から始めて秋にはまだ届かない。ここからが本領発揮。
- あきらめなくて正解!
- どれだけ志望校に入りたいかの熱量が大事!
- 反対されたら困るからと、親に見せなくて正解!
長男は「行きたい大学のランクも落とさないし、私立も受けない。」「落ちたら浪人する。」と決めました。行きたい大学がないから、と。
「浪人してかかったお金は働いたら返してよ」と言っても「それでいい」と腹をくくっていました。
親も少しずつ成長します。長男の時は「金銭的に北海道の大学にして」と条件をつけていました。ところがこの後一人暮らしをするようになり「どうせ一人暮らしをするなら全国どこに住んでも変わらない」ということを学びます。次男には最初から北海道にこだわらず、どこでも行きたい学校でいいと言えていました。長男にももっと選択肢を与えてやればよかったかな、と思いつつも希望の大学に入れたのでよかったです。

自分を信じて大丈夫!頑張っているのは自分なんだから!
親になんと言われようと自分を信じて頑張れ!
スマホや「オンラインコンテンツ」の普及。「神授業」の「スタサプ」が加わった5歳下次男(朝型)の勉強法。
「YouTube」「スタサプ」スマホ動画で勉強するのが当たり前の時代に

5歳下の次男の時代には世の中が大きく変わっていました。コロナと共に過ごし、スマホやタブレットでのオンラインコンテンツが普及していました。スマホの画面も大きくなり、お年玉を貯めてタブレットを買うくらいタブレットもとても身近な物になっていました。
そんな中で次男がやってみたい、と見つけてきたのが「【公式】スタディサプリ高校・大学受験講座」です。
スタサプの活用法。メリット。デメリット。
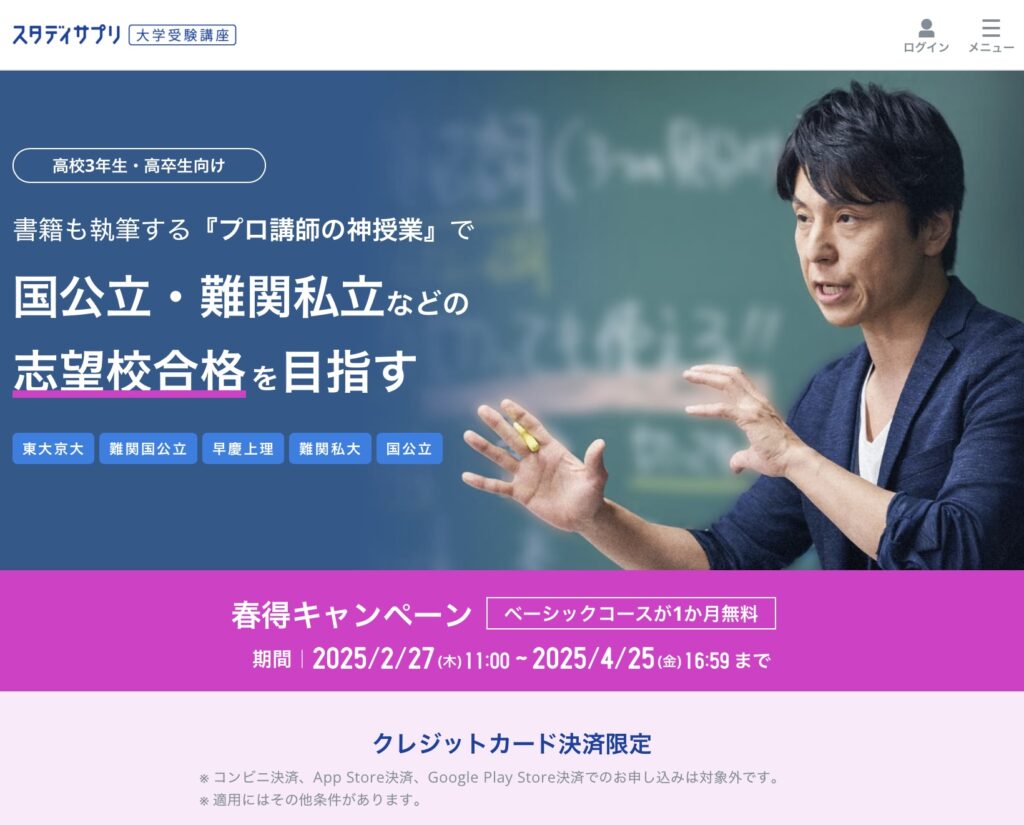
スタサプのメリット
- 自宅で学習できる→塾に通う時間のない部活生にぴったり!
- 日中寝てしまって聞き逃した授業も完璧に網羅できる
- 参考書と違って動画なので、目と耳で学習でき記憶に残りやすい→人の声って記憶に残る
- クセ強めな先生が多い→記憶に残る→倍速で聴いてさらにクセ強調されて記憶に残る
- 圧倒的コスパ→年払い21,780円(月あたり1,815円) ※塾なら半年ごとに60万円なんてこともありますよね
- 全ての教科が見放題
次男の場合は、テスト1週間前で部活が休みになったときに倍速で詰め込み勉強していました。
疲れてベッドに横になりながらでも勉強できるのもいいところです。ただこれは表裏一体で、そのまま寝落ちする危険もあります。
普段は全然使わないのに年払いできるのは圧倒的安さのおかげでした。月払いもできるけど、入ったり退会したりは面倒なので年払いにしました。もしかしたら使うこともあるかもしれないですしね。
スタサプのデメリット
- 強制的に勉強させられるものではないので、自主的にできない子には向かない
- 参考書などと違って、分からないところだけピンポイントで調べられない→分かっているところも含めて動画を見ることになっちゃう
これくらいですかね。総じてメリットの方が圧倒的に多いです。
【公式】スタディサプリ高校・大学受験講座
今ならクレジットカード決済限定で春特キャンペーン中です
初めての方も、再契約の方もベーシックコースが1カ月無料!
2025/2/27(木)11:00〜2025/4/25(金)16:59まで
通常2週間の無料体験がまるまる1カ月お試しできるようです。
新学期が始まってやる気があるうちにお試ししてみるのもいいかもですね。
ちなみに次男は朝型なので、夜は早く寝て5時起きで勉強したりしていました。
次男が現役合格できた一因は、間違いなくスタサプのおかげです。
最終的には本人がどうしたいか。自分の人生は自分で責任を負うもの。
2024年次男流「進学先の決め方」
2024年に次男が進学先を決めた方法はこちらで詳しくまとめています

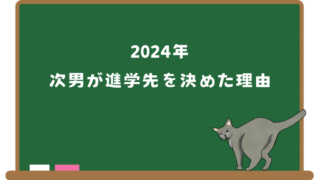
高卒でも構わない。自分の生きたいように生きたらいい。

ここまで大学受験を前提に話を進めてきましたが、決して親が強制したわけではありません。夫も私も高卒ですし、金銭的なことを考えれば、高卒で就職してくれた方がありがたいくらいです。もし本人が高卒で働くことを望むなら、それを全力で応援します。結局のところ、進路は子ども自身が決めること。自分の未来は自分で切り開くものです。
親が子どもの人生を生きることはできません。
子どもの人生の責任を取れるのは、子ども自身です。
私自身、高卒で就職し、給料をもらえるようになったことがとても幸せでした。貧しい家庭で育ったので「親に育ててもらう立場からの解放感」を強く感じたのを覚えています。
ただ、現代の状況は子どもに伝えておいた方がいいと思います。
例えば、
- 昔よりも進学率が高くなっていること
- 高卒よりも大卒の方が選べる会社の幅が広がること
- 一般的に、大卒の方が生涯年収が多くなる傾向があること
長男が大学を選んだ理由は、当時目指していた放射線技師になるために大学での学びが必要だったからです。
こんな子は大学に行った方がいいと思います。
- 将来の目標が決まっていて、そのために大学の学びが必要な子
- まだやりたいことがわからない子
大学に通うことで「やりたいことが見つかる」こともあれば、「やりたいことが変わる」こともあります。それは、視野が広がった証拠です。
長男も「放射線技師になりたい」と思って大学へ進学しましたが、最終的に就職したのはコンサル業界です。高卒の私たち親はコンサルという職業を知りませんでした。なので長男ももちろん知らず、高校生の時点では候補にすら挙がらなかった職業です。高校生までの狭い世界ではなく、大学で広い世界を知り、より興味のあるやってみたい職業を見つけました。
次男は北海道から九州の大学に進学し、まったく異なる土地柄に刺激を受けています。北海道にはない「歴史」を感じることもあるようです。間違いなく視野が広がっています。学びを深める中で、海外に行きたくなるかもしれないし、起業を考えるかもしれません。
大学の良さは、学びの機会だけでなく、時間的な余裕(猶予期間)があることかな、と思います。
子どもが「なりたいもの」を見つけたときに、それを選べる立場でいられるよう、親としてサポートしてあげてくださいね。

高卒でも大卒でもいい!みんながやりたいことを見つけて毎日幸せに生きることが大事だよ!